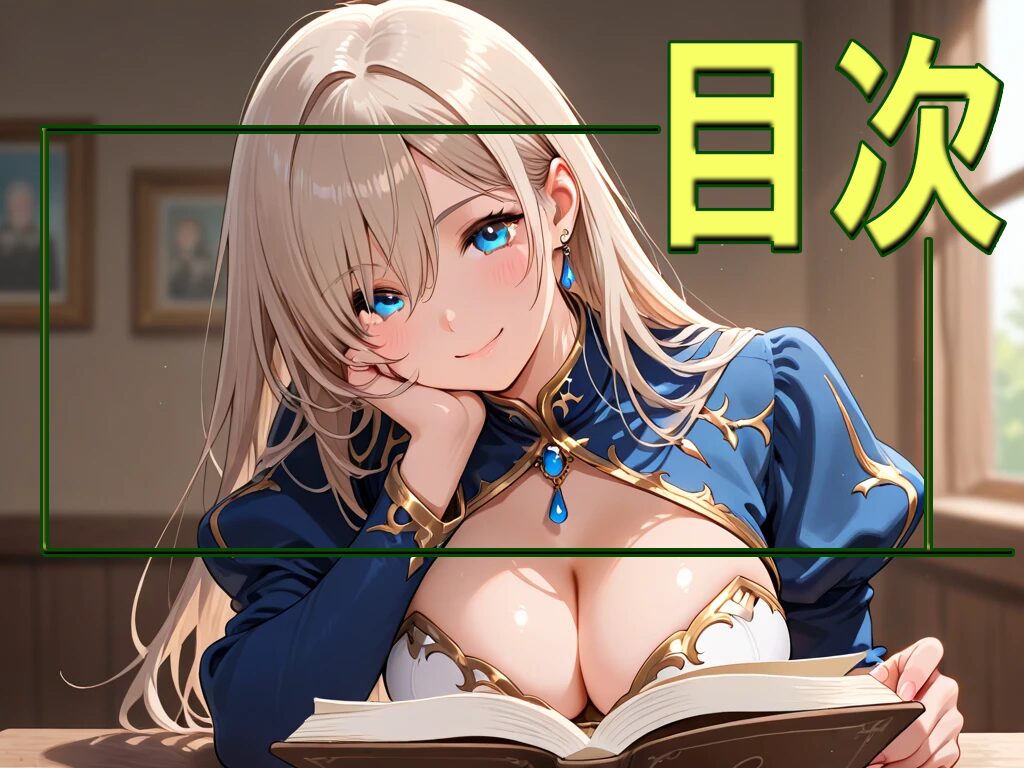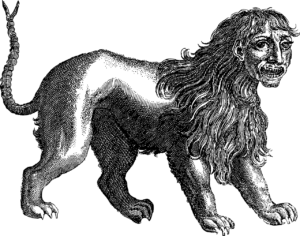2021年もコロナ禍が続く厳しい日々です。
そこで私の好きなファンタジー世界において、このような災害が訪れた時、人々はいったいどうするだろうかと考えました。
もちろん回復を願うでしょう。
その時きっと、その世界の人々はあるモンスターの治癒能力に期待を寄せるかもしれません。
ユニコーンはご存知でしょうか?
そうです。
角の生えた白馬のイメージです。
いまや「ファンタジー」と検索すると高確率でこのユニコーンの画像がヒットするようになりました。
しかしこのユニコーン、決して平和の象徴でも、優しい幻獣でもないのです。
それどころかひどく獰猛で、人間にすら危害を加える害獣であるとされています。
凶暴なユニコーン退治の英雄譚も存在するほどなのですよ。
なぜ人間に対して敵対するのでしょうか?
それは人間たちがユニコーンの角を狙って彼らをつけ狙うからにほかなりません。
ということで今回はファンタジーの象徴にもなったユニコーンについて調べてみました。
ファンタジーの知識があれば、より楽しい!
ぜひ最後までお付き合いくださいませ。
そもそもユニコーンとはなんぞや?

ユニコーンとは、額に一本角を生やした白馬のモンスターです。
- 獰猛な性格で、象やライオンにもたじろぐことなく、突進して一突きにしてしまいます。
- 最大の特徴である額の角は「万病に効く」とされ、貴族や盗賊から常に付け狙われています。
- 純潔の乙女、「処女にしか心を開かず」、人間が飼い馴らそうとすると悲しみのあまり死んでしまいます。
- 知能も高く、精霊のように意思の伝達ができます。
- 魔法に対する耐性も高く、人間の置いた罠などにもかかりません。
- 作品によっては「魅了(チャーム)」の魔法を使えたり、1日1回限定で近距離のテレポート能力を持つこともあります。
これが令和の日本における一般的なユニコーンのイメージでしょうか。
ユニコーンの歴史

ユニコーンの名の由来はラテン語で、ひとつを意味する「ウヌス」、角を意味する「コルヌス」から来ています。
また、一角獣を「モノケロス」と表すこともあります。
ユニコーンが最初に文献に登場するのは紀元前5世紀。
古代ギリシアの歴史家クテシアスの著した『ペルシア誌』です。
そこに書かれたユニコーンの容姿は以下の通り。
身体は白いロバのよう、頭部は赤く、目は青い。
角の長さは50センチで、先が赤く、中間は黒く、根元は白い。
今の白馬のイメージとはかけ離れていますよね。
ちなみに肉は酷く苦いため食用には適さないそうです。
ユニコーンを食べるという発想、なかったわ。
続く1世紀(77年ごろ)、ローマの大プリニウスが『博物誌』にてユニコーンに触れています。
出ました『博物誌』。
このブログでも何度か登場していますね。
プリニウスはユニコーンについて以下のように記しています。
馬のような体、象のような足、猪のような尻尾、鹿のような頭。
黒くて長い一本角の長さは1メートル。
とまあこんな感じで伝えています。
馬ではないですよね、これ。
それから時代は進み、ユニコーンはイギリスのドルイド僧や、ヨーロッパの錬金術師にも研究されるようになります。
この頃には今と変わらないユニコーン像、いわゆる白馬で、額に黒いらせん状の角、ヤギのヒゲ、ふたつに割れた蹄といったイメージになりました。
ユニコーンは紋章のモチーフにもなっています。
紋章に選ばれるのはかなり人気が高い証拠ですが、スコットランド王ジェームス4世は王家の紋章に2頭のユニコーンが向かい合った図柄を採用。他にもイギリスのエリザベス女王も採用しているそうです。
ユニコーンは月の象徴として、太陽の象徴である獅子と戦いあっているとまでされました。
そしてこの当時、ユニコーンはインドやエチオピアに実在すると信じられていました。
13~14世紀、探検家マルコ・ポーロは『東方見聞録』にて、ユニコーンは「バスマン王国」(スマトラ島にあったとされる)に多数生息していると書いています。
現在ではアラビアの砂漠に棲むオリックスなどの動物が、伝聞されていく過程で変化したものだろうという説が優勢です。
ユニコーンの浄化能力

ユニコーンの最大の特徴とも言える額の一本角ですが、この角は突進して突き殺す武器としてだけでなく、それ以上に「浄化能力」に価値があります。
- 邪悪な力を振り払い、どんな病気も治す。
- 毒で汚染された泉にユニコーンが入り、角で十字を切ったところ泉が飲めるほどに浄化される。
- この角はユニコーンから切り離しても効力を失わない。
これほどの価値のあるユニコーンの角です。
多くのハンターがユニコーンをつけ狙い、多くの貴族が大金を払って角を買い求めました。
なんと19世紀までロンドンではユニコーンの角を粉末にした薬が本当に売られていたというから驚きです。
ユニコーンの角による浄化能力は、主に「毒」の中和に最適だったそうです。
さらにこの角を加工すると毒を見分けるアイテムに早変わりします。
- 角で作った杯に毒を注ぐと割れてしまうのですぐにわかる。
- 短剣の柄を角で作ると、そばに毒物があると柄が湿り気を帯びるのですぐにわかる。
常日頃、暗殺におびえる貴族連中はこの角が欲しくてたまらなかったようですね。
ただ実際はほとんどがニセモノでした。
多くは「北海のイッカククジラのツノ」や「アフリカの鹿の角」「牛の蹄(ひづめ)」であったようです。
当然何の効果もありません。
あくどい商人に金持ち連中が騙されていたのです。
ユニコーンの捕まえ方

ユニコーンを捕まえる、たったひとつの冴えたやり方というものがあります。
中世ヨーロッパにおいて、聖書と並ぶほどに読まれた教本『フィシオロゴス』によると、ユニコーンは唯一、処女にだけなつく、とあります。
やり方は簡単で、森の泉に処女をひとり座らせておくと、どこからともなくユニコーンが現れ、処女の膝枕で眠ってしまうというのです。
獰猛な性格で、一突きで象も殺してしまう、普段固い岩で自身の角を研いでいるという戦闘狂たるユニコーンが、です。
どうやら普段からハンターに狙われるユニコーンは、処女の膝枕でそのストレスから解き放たれ気が緩んでしまうらしいのです。
まあ、気持ちはわかりますが。
とにかくこれがユニコーン捕獲の最適解です。
ただし、囮に使う乙女が本当に処女ではなかった場合、ユニコーンは怒ってその女を突き殺してしまうそうです。
なのでもし実践しようと思っている人がいたらそこは正直になってお気をつけくださいね。
ちなみに、このユニコーンの処女好きという性格から「貞潔」というイメージが付き、「貴婦人とユニコーン」というテーマが絵画によく選ばれるようになったそうです。
中国の麒麟とユニコーン

実はユニコーンは中国の霊獣である麒麟と同一視されたりします。
麒麟と言えばかなりの高ランクモンスターですよね。
その麒麟とユニコーン、正直見合わないと思いませんか?
これにはひとつの逸話があって、それはあのモンゴル帝国のチンギス・ハーンなのです。
チンギス・ハーンが軍隊を駆り山中を移動している際、鹿のような一角獣に遭遇しました。
「角端(かくたん)」と呼ばれる麒麟の一種だったそうです。
これが中国にも(麒麟なのに)ユニコーンがいるとされ、結果同一視されるようになったようです。
まあ神々だってあっちこっちで同一視されるものだし、多少はね。
ところでこの逸話からか『ウルティマオンライン』というゲームでは、男性は麒麟を手懐けられるがユニコーンは手懐けられない。
女性はユニコーンは手懐けられるが麒麟は手懐けられない。という設定を取り入れているとか。
ファンタジーの設定を作る際にはこういう所からもいろいろ引っ張ってくるものなのですね。
ユニコーンが出てくる作品
『機動戦士ガンダムUC』
ガンダムユニコーンは白い機体に一本角のアンテナが特徴のモビルスーツです。
主人公パナージが搭乗します。
たしか肖像画かなんかに「貴婦人とユニコーン」が描かれているとか劇中であったような。
『テイルズオブファンタジア』
テイルズオブシリーズの第1作目。
パーティーの二人の少女、ミントとアーチェがユニコーンをおびき出すため囮となるイベントがあります。
しかし、ここでハーフエルフの少女アーチェから思わぬ発言が飛び出し……
『レジェンド/光と闇の伝説』
リドリー・スコット監督、トム・クルーズのデビュー作であるファンタジー映画です。
決して触れてはならないとされるユニコーンの角。
王女リリーが触れてしまったことで魔王が復活するというわかりやすい物語です。
85年の映画ですがとても映像がキレイで、深夜にひとりで観るにはうってつけです。
『キン肉マン』
王位争奪戦編でロビンマスクが使いだした技です。
アノアロの杖と言って炎を操れるロビン家の家宝です。
その杖を額に装着するとユニコーンヘッドと言ってロビンマスクが一本角になります。
まあ、かっこよかったんです。まさかキン肉マンマリポーサに勝つなんて思わないじゃん。
『ユニコーンの乙女』
原作は『ソードワールド短編集』に掲載された水野良先生の短編小説です。
青木邦夫先生により漫画化もされています。
森林衛士のジュディスはユニコーンのアンウェンと共にユニコーンを殺した暗黒神官を追います。
しかし返り討ちに遭いジュディスは囚われの身に。
アンウェンは毛嫌いしていた同じ森のドルイド僧ケニーに仕方なく助けを乞います。
ケニーは戦乙女と炎の魔神を使う精霊使いだった。
まとめ

いかがだったでしょうか。
ユニコーンってもはや説明不要の超有名モンスターですよね。
なんというか、一本角と言えばユニコーンみたいなところまで来てると思うんです。
ファンタジックな絵を入れようと思えばユニコーンは高確率で採用もされるでしょうし。
でも本来のユニコーンというのはすごく獰猛で危険な存在でした。
それもあくどい人間たちにより、その角が狙われたからにほかなりません。
結果ユニコーンも純潔の乙女にしか気を許さないという小難しいキャラになってしまったと思います。
それをキャラが立っていると観るのは創作者の勝手でしょうか。
みなさんもぜひユニコーンのような歴史と能力を持った幻獣を創造してみてください。
また変わったユニコーンを生み出してみるのも面白そうですよね。
それではまた!