男を王にし、堕落させ、国を亡ぼす。
「傾国の美女」と言えば……歴史上枚挙に暇がありません。
しかし、九本の尻尾を持つと言えば、すぐさまあの大妖怪が浮かんできます。
九尾の狐。
大変有名で、大変に協力で、雑魚扱いなど微塵もされない。
それでいて妖狐としての戦闘力よりも、美女として権力を操る謀略の方が恐ろしい。
強くって、賢くって、美しい。
ファンタジーの知識を知れば、より楽しい!
それでは今回も皆さまの創作活動やゲームなど、没入感の参考になることを願って。
ぜひ最後までお付き合いくださいませ。
そもそも九尾の狐とはなんぞや?

九尾の狐とは、中国発祥であり、九本の尾を持つ狐の大妖怪のことです。
まず中国では、
- 狐は50年生きると女性になり
- 100年生きると美女になり
- 1000年生きると天狐となり、神と同等の力を有する
と言います。
その「天狐」になるには大量の精が必要なので、美女に化けて人間の国全体をたらし込むのだそうです。
中国では「狐の精」という存在が信じられており、霊力は尾にあるとされていました。
漢の時代までに書かれた地理書『山海経』によると、「九つの尾と九つの首、虎の爪を持つ狐のような妖怪が青丘国におり、人間を喰う」とあります。
一般より「多い」ということは単純に「強い」という事を意味します。
なので尾の本数が多ければ多いほど強い、という設定が生まれるわけです。
どこの妖怪?

お伝えしてますとおり、九尾の狐は古代中国発祥でございます。
後述しますが、この妖怪は日本にも大変ゆかりのある為、日本の妖怪と思われる節も見受けられます。
しかしそんな程度ではありません。
この狐の大妖怪は、アジア一帯をまたにかける存在なのです。
それだけ人間界に影響を与えたこの妖怪、恐ろしさはその戦闘力ではなく、人心を惑わす奸智にあります。
しかし最初からそうだったわけではないのです。
「瑞獣(ずいじゅう)」といって、中国では吉兆を伝える神獣であったのが始まりです。
夏王朝のはじまり

夏(か)王朝とは(判明している限り)中国最古の王朝です。
『封神演義』でも有名な、あの殷(いん)よりもさらにひとつ前の王朝です。
割りと近年になってから実存が確認できたかな、てぐらいあやふやな感じらしいのですが。
その時代に禹(う)という男がいました。
父の跡を継いで黄河の治水工事に尽力し成果を上げた人物です。
仕事に没頭するあまり婚期を逃し、中年になっても独り身でした。
令和の日本なら普通ですけどね。
この当時流行っていた歌があって、「九尾の狐を見ると王になり、塗山(山ではなくて地域の名称)の娘と結婚すると家が繫栄する」というものです。
そして禹は塗山の女嬌(じょきょう)という名の娘と結婚し、当時の帝から後を継ぐよう言われ、夏王朝を開いたという事です。
この話の九尾の狐はまだ伝承を伝える程度の登場に留まっていますね。
殷王朝を滅ぼした妲己

ここから凄惨な歴史の幕あけです。
紀元前17世紀、先の夏王朝を滅ぼした殷(商)王朝。
600年ほどが過ぎた紂王(ちゅうおう)の時代。
名君として才気あふれていた紂王に、有蘇氏(ゆうそし)から降伏の証として娘が献上されました。
それが妲己(だっき)です。
ですがこの時、中国の女神女媧(じょか)に無礼な発言をした紂王を懲らしめるため、妖狐が妲己に憑りついたと言われます。
後は有名な話ですが、妲己におぼれた紂王が国政をないがしろにして放蕩三昧。
酒の池や木に肉を吊った庭での「酒池肉林」や、油を塗った銅柱に火をつけ罪もない人に抱かせる「炮烙の刑」など。
残虐な遊びが後を絶ちません。
当然の如く、やがて西方を治める武王(ぶおう)に討たれて殷は滅亡します。
さらにちなみにこの紂王の暴虐は史実かどうかはわかりません。
その後の周王朝が殷を討つために紂王を悪者に、都合よくでっち上げたという可能性もあるわけです。
歴史において「いい人」「悪い人」という判断は時代によって違います。
周の幽王を翻弄した褒姒

殷の次、周王朝の12代目幽王は、ひとりの女を寵愛したため、后と太子を捨てこの女に傾倒しました。
その女が褒姒(ほうじ)です。
彼女は竜を体内に宿した少女がひとりで産んだとされ、褒国の貧しい夫婦に拾われ育てられ、やがて褒国から貢物として幽王に送られました。
その美貌に目を奪われた幽王は、彼女の関心を引こうとあの手この手を尽くすのですが、彼女は決して笑わない。
あるとき緊急を知らせる狼煙と太鼓を打ったところ、各地の諸将が慌ててはせ参じたことがありました。
ですが実際は何事もなかった。手違いだったのでしょう。
だがその諸侯の慌てぶりが可笑しかったのか、ついに褒姒が笑ったのです。
「これだ!」
そう思った幽王は、何度も何度も同じことをして諸将を呼び寄せました。
彼女は笑わせられましたが、諸将は怒らせてしまいました。
そんなある日、本当に軍勢が攻め寄せてきたのです。
攻めてきたのは幽王が捨てた后の父親の軍勢でした。
慌てて幽王は緊急招集を掛けますが、もはや誰もやって来てくれることはなく、あわれ幽王は惨殺されてしまいましたとさ。
オオカミが来たぞ、的なね。
こちらも直接の記述はないけど九尾の狐の逸話に列挙されます。
天竺で百人の王の首をねだった華陽夫人

まだ続きます。お次はインドです。
殷の妲己から抜けた九尾の狐は遠く天竺(インド)へ落ち延びます。
その地で天羅国の班足(はんぞく)王に気に入られ、華陽夫人として振舞います。
僧侶を1000人柵の中に押し込めると獅子を放ち食わせたり、近隣の王100人の首をねだったりしました。
それに応えられる班足王も悪鬼のように強い男だったのですが、信心深い隣国の王が読経を始めると九尾の狐の正体がバレ、一目散に逃げ出しました。
大陸を追われた九尾の狐は最後に日本へとやって来るのです。


ついに討たれた玉藻前

長かった九尾の狐の旅ももうすぐ終わりです。
時代は流れ735年。
遣唐使、吉備真備(きびのまきび)の船に密航し日本に渡ると、なんと300年以上も何処に潜伏してしまいます。
そして時代は流れ平安末期。
鳥羽上皇の宮女でありながら寵愛を受けた女がいました。
彼女の名は玉藻前(たまものまえ)と言い、もちろん九尾の狐が憑りついていました。
だんだんと病に伏せるようになる鳥羽上皇(このころは法皇かな)を見舞った陰陽師の安倍泰成(あべのやすなり)が正体を見破ります。
逃げた玉藻前を追う討伐軍が編成され、下野(しもつけ)の国、那須野にてついに退治されました。
この玉藻前は江戸時代などに歌舞伎や能の題材となった創作ですがモデルはいます。
鳥羽上皇の后である藤原得子(とくし/なりこ)です。
この辺の人物相関や血縁関係は入り乱れているので理解は難しいのですが、とにかく自分の子を天皇にしようと謀略を尽くしたんです。
その結果、崇徳天皇を菅原道真、平将門と並ぶ日本三大怨霊に仕立て上げてしまいました。
この辺りは大河ドラマの『平清盛』が見ていて面白かったですね。
その後の九尾の狐

さて、ついに討ちとられた九尾の狐ですが、それだけで事態は収束しませんでした。
那須野で討たれた九尾の狐ですが、その体は巨大な石となり周辺に毒をまき散らしたのです。
近づく者を死に至らしめる「殺生石」へと変化したのですね。
ところがこの殺生石、玄翁(げんのう)と名乗る和尚が見事粉々に打ち砕くことで鎮めてみせたというのです。
トンカチのことゲンノウって呼ぶ謂れはここから来てるそうですよ。
DIY好きな人にしか伝わらんかな?
さて下野の国とは現在の栃木県です。
栃木県那須町湯本にはまだこの「殺生石」が史跡として残っています。
でも今は大丈夫ですから安心してくださいね。
※2022年3月6日追記
この殺生石ですが、なんと割れてしまったという事です。
関係者によると数年前からひび割れを確認していたそうで、今回は自然に割れたと推測されています。
しかし、まさかと思いますが、相手は大妖怪ですからね。
1000年の時を超えて、なんてことももしかしたら……
殺生石 真っ二つ 以前からひび、自然現象か 那須(参照 下野新聞SOON)
九尾の狐の出てくる作品
枚挙に暇がない!
とにかく数多くの作品に登場します。
しかもそのエピソードゆえにほぼ雑魚扱いはされません。
ボスクラス、または味方レギュラークラスがほとんどです。
いくつか絞ってご紹介させていただきます。
『うしおととら』
もう絶対にコレでしょう!
バケモノを払う「獣の槍」を持つ少年潮(うしお)と、火と雷を操る最強の化物とらが戦うマンガのラスボスです。
「白面の者」と呼ばれる九尾の狐は最強のバケモノとして日本全土を陥れます。
ちゃんと中国、インド、平安の日本でのエピソードも踏まえてます。アレンジ効いてますが。
このマンガのすごいのはなんといってもその最終決戦。
主役たちと妖怪たちだけでなく、日本政府や自衛隊、アメリカ、全国民をきっちり巻き込んで盛り上げてくれます。
妖怪ものが好きなら今でも絶対に外せない逸品です。
『封神演義』
藤崎竜先生のマンガ版の事です。
主人公太公望が仙人の武具である宝貝(パオペエ)と多くの仲間を駆使して仙女妲己と殷王朝相手に戦うマンガです。
古代中国が舞台ですが全体的にSFチックです。
女媧まで出てきます。
妲己は敵ですがジャンプ屈指のヒロインでもあります。
ちなみにハンバーグ好きな方は閲覧注意かもです。
『Fate/EXTRA』
FateシリーズのうちPSPで発売されたのがこのエクストラです。
三人のサーヴァントからひとりを選ぶのですが、キャスター枠が玉藻前ですね。
狐耳の女の子です。
キャス狐と呼ばれ親しまれていました。
ゲームでは……すいませんセイバールートしかプレイしてません。

まとめ
いかがだったでしょうか。
もう情報量が多すぎて書くのが大変でした。
中国の歴史や地理も調べるのでほんとに大変でした。
だからこそ、この記事だけ読めばだいたいのところはつかめると思います。
これだけご紹介したエピソードなんですが、実は、全部フィクションなんですよね。
当然ですよね、すいません。
けど例えば殷王朝の崩壊や、鳥羽法皇の病や継承問題は事実であるわけで。
後の文学などでそこが融合されて今日まで語り継がれているんですよね。
これって創作におけるヒントとも取れませんでしょうか?
まだまだ九尾の狐は創作界では大活躍してくれるはずです。
皆さんの手で新たな九尾の狐を生み出してはみませんか?
その時は是非教えてくださいね。
それではまた!

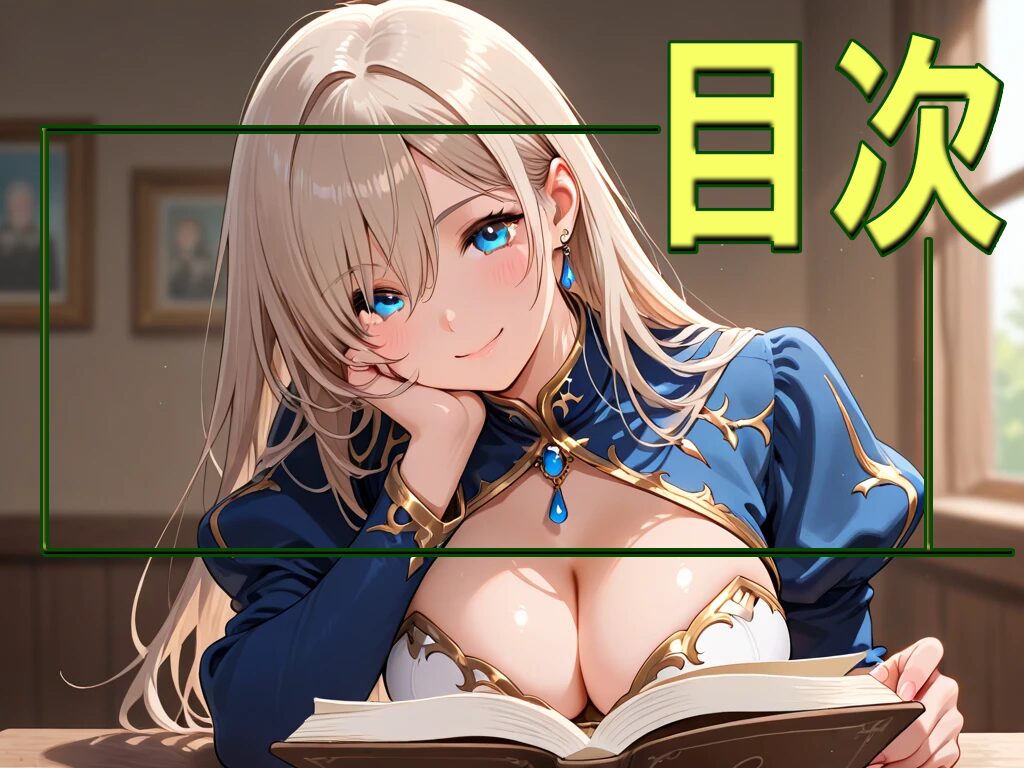




















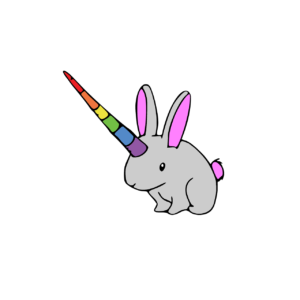

コメント